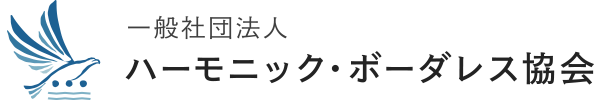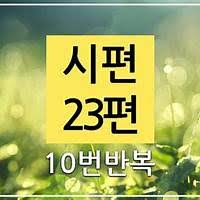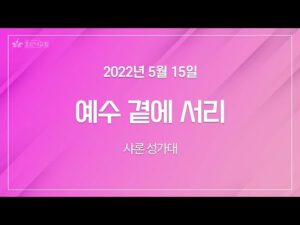テレクトノンやフナブ・クを21を理解する前提としてイエス・キリストの事を知らなければなりません。
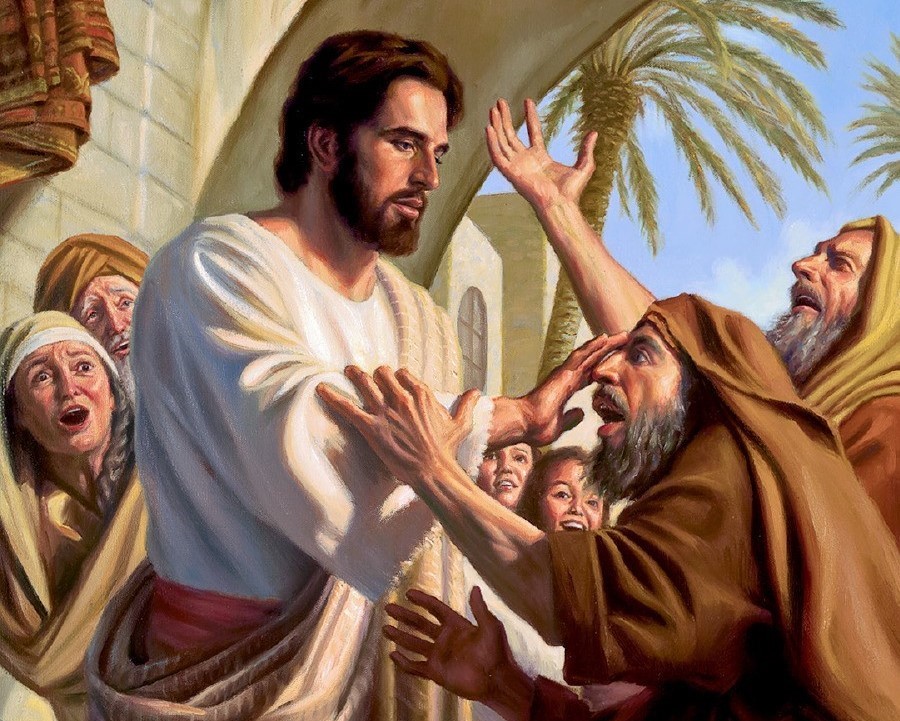
イエス・キリストの哀れみ(スプランクニゾマイ)の語を12回だけ用いられている。
キリスト中心的に神観を受けとめていく最も適切な方法は、まず新約聖書におけるイエス・キリストについての証言に耳を傾けることであると考えられる。それは、祈りつつイエス・キリストの言動に対して用いられている言葉に聞き、文脈の中で、イエス・キリストがどのようなお方であるかということを思い巡らすことである。
ここで、新約聖書に用いられている「スプランクニゾマイ」というギリシア語の動詞に注目したい。この語は共観福音書において、12回だけ用いられている。しかも、いずれもイエス・キリストの心の動きに対してだけ用いられている言葉で、決して人に対しては用いられていない。
新改訳聖書において、「スプランクニゾマイ」は、「かわいそうに思われた」、「かわいそうに」、あるいは「深くあわれんで」、「深くあわれみ」、と翻訳されている。しかしこの言葉は、内臓・はらわたを指す「スプランクナ」ということばから派生した動詞で、多くの方がすでに指摘しているように、「内臓が揺り動かされる」、「はらわたわななく」という激しい痛みのニュアンスを持つ言葉である。ギリシャ語の中にいくつかのあわれみを意味することばがあるが、中でもこの「スプランクニゾマイ」は最も強いあわれみを表現することばである。
①羊飼いとしてのイエスの、失われていた羊に対する深い愛と宣教の情熱を表わす
また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。(マタイ9:36、マルコ6:34)
ここでスプランクニゾマイは、12弟子を遣わす直前に、イエスが、羊飼いのない羊のような、そして弱り果てて倒れている群衆を見られた時の、心の動きを表現している。苦しめられ、疲れ果てている群衆を見られてのイエスの心の動きで、「はらわたが震えるほどのあわれみを覚えられた」というような意味だと思われる。
②イエスの後を追ってくる病んでいる人々を癒す行為
イエスは舟から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深くあわれんで、彼らの病気を直された。(マタイ14:14、マルコ6:34)
ここでもスプランクニゾマイはイエスの心の動きに対して用いられている。イエスの後を追ってくる多くの群衆の姿がイエスの目に映った時、イエスの心の中に生じた動きである。その後、イエスは病気の癒しを行っている。
③空腹の群衆を見られたイエスの口から、弟子たちに対して出た言葉
イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。「かわいそうに、この群衆はもう三日間もわたしといっしょにいて、食べる物を持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。」 (マタイ15:32、マルコ8:2)
その時にイエスの目に映っていたものは、三日間何も食べずにイエスについて来ている故に、極度の空腹を覚えて疲れ果てている多くの群衆たち(女と子どもを除いて、男四千人)の姿であった。この群衆はイスラエルの神を賛美していた異邦人だったと考えられる。空腹で倒れそうになっている異邦人の群衆を見ても、何も感じていない弟子たちとの強烈な対比が描かれている。イエスはその後、4千人以上の群衆に対する給食の奇跡をなさった。
④赦し難い罪の負債を徹底的に赦す
しもべの主人は、かわいそうに思って、彼を赦し、借金を免除してやった。 (マタイ18:27、マタイ18:21)
このたとえをイエスが話されたきっかけは、赦しについてのシモン・ペテロの質問『主よ。兄弟が私に対して罪を犯したばあい、何度まで赦すべきでしょうか。七度まででしょうか。』である。これに対してイエスは『七度まで、などとはわたしは言いません。七度を七十倍するまでと言います。』、実際には無制限に赦すということ!)という言葉をもって質問に答え、たとえを語り始めている。
⑤二人の目の見えない人たちの嘆願に応えて癒される
イエスはかわいそうに思って、彼らの目にさわられた。すると、すぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて行った。( マタイ20:34、マルコ10:46、ルカ18:35)
イエスの目に映ったものは、「主よ。私たちをあわれんでください。ダビデの子よ。」と叫び立てて懇願する、道ばたにすわっていた2人の目の見えない人であった。イエスは立ち止まって彼らを呼び、「わたしに何をしてほしいのか。」と言われた。彼らは「主よ。この目をあけていただきたいのです。」とイエスに言った。この言葉を聞かれた時、イエスはスプランクニゾマイという言葉で表現される心からのあわれみを抱かれ、熱心にイエスに懇願する彼らの目にさわられ、そして彼らの目を開いて下さったのである。
⑥ひとりのらい病人の信仰による嘆願に応えられ、癒しをもたらす
イエスは深くあわれみ、手を伸ばして、彼にさわって言われた。「わたしの心だ。きよくなれ。」(マルコ1:41)
イエスの目に映ったものは、イエスのもとに来てひざまずいて嘆願するひとりのらい病人であった。彼は「お心一つで、私はきよくしていただけます。」と信仰をもってイエスに願った。当時、らい病人に触れればその人も汚れると考えられていた。しかしイエスは、あえて彼にさわられた。それは、イエスがその病人に対して心の底から揺り動かされるほどの深いあわれみを持っていた表われであると考えられる。
⑦羊飼いとしてのイエスの、失われていた羊に対する深い愛を表わす
イエスは、舟から上がられると、多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深くあわれみ、いろいろと教え始められた。 (マルコ6:34、マタイ14:14)
イエスと弟子たちは人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったので、舟で寂しい所へ行って、しばらく休もうと試みていた。しかし群衆は、舟に乗ったイエスを徒歩で追いかけてきたのである。イエスの目に映った羊飼いのいない羊のような多くの群衆によって、スプランクニゾマイで表現される心の底からあわれみが湧き上がった。そしてイエスは神の言葉によって、群衆を養われたのである。
⑧空腹の群衆を見られたイエスの口から、弟子たちに対して出た言葉
「かわいそうに、この群衆はもう三日間もわたしといっしょにいて、食べる物を持っていないのです。 (マルコ8:2、マタイ15:32)
異邦人の地で、大ぜいの人の群れが集まっていたが、食べる物がなかったので、人々は3日も何も食べていない状態であった。6:34-44の場合は、その日一日、しかもその日の夕方に食べ物がなかった場合であるが、ここでは3日間も食べ物がなかったのである。この点で、5,000人の給食と異なる。イエスは群衆の痛みを感じることが出来ない弟子たちを呼んで、愛の働きへとチャレンジされた。
⑨イエスに対しての不信仰な祈りの中で用いられた
この霊は、彼を滅ぼそうとして、何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もし、おできになるものなら、私たちをあわれんで、お助けください。」(マルコ9:22)
汚れた霊を追い出してもらうための嘆願の祈りの中で、この言葉が使われているスプランクニゾマイは、イエスに対しての懇願の言葉の中に用いられている。しかし、その願いは「ただ、もし、おできになるものなら、私たちをあわれんで(スプランクニゾマイ)、お助けください。」という非常に不信仰な願いであった。これは弟子たちが癒すことができなかったのを見て、失望していた時に出た父親の言葉であると考えられる。しかしイエスはそれに対して、「できるものなら、と言うのか。信じる者には、どんなことでもできるのです。」と叱責される。するとすぐに、その子の父は「信じます。不信仰な私をお助けください。」とイエスに叫んだ。イエスはその後、汚れた霊を追い出されるという御業をなさった。
⑩ひとり息子の死を嘆き悲しんでいるナインのやもめを見た時のイエスの思い
主はその母親を見てかわいそうに思い、「泣かなくてもよい。」と言われた。 (ルカ7:13)
イエスの目に映ったものは、ひとり息子に先立たれ、やもめとなって出棺に立会い、嘆き悲しんでいるナインの母親の涙であった。ひとり息子の死に嘆き悲しんでいるナインのやもめを見られたときに、イエスが持たれた、はらわたが震えるほどの深いあわれみを語っている。
⑪良きサマリヤ人のたとえ:強盗に襲われた敵の隣人になった動機―(民族間の・神と人との間の)敵意の壁を打ち破る
ところが、あるサマリヤ人が、旅の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、 … (ルカ10:33)
このたとえが語られた背景は、ある律法学者がイエスをためそうとして「先生。何をしたら永遠のいのちを自分のものとして受けることができるでしょうか。」という質問によって始まる。それに対して、イエスは「律法には、何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。」と言われた。すると彼は「『心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』また『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』とあります。」と模範解答を答えたのである。それに対してイエスは「そのとおりです。それを実行しなさい。そうすれば、いのちを得ます。」言われた。しかし彼は、自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。「では、私の隣人とは、だれのことですか。」と逆にイエスに問い掛けるのである。 おそらく彼には、隣人を限定し自分の好きな人々ということにするなら、自分は隣人を愛しているという自負があったと思われる。「では、私の隣人とは、だれのことですか。」という質問に対して、イエスは良きサマリアのたとえを語ることによって答えられたのである。イエスがこのたとえを彼に語った理由は、彼に憐れみによって生きてないことを悟らせ、神の憐れみによって永遠のいのちに生きるように招くためであったと思われる。
⑫父が遠くに帰ってきた放蕩息子を見つけた時の思い ―失われた息子を見出した父親の歓喜を表わす
こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。(ルカ 15:20)
15:1―3節の文脈に、イエスがこのたとえを話されたきっかけが書かれている。またそこには、誰に対してイエスがこのたとえを語られたのかということも明記されている。
15:1 さて、取税人、罪人たちがみな、イエスの話を聞こうとして、みもとに近寄って来た。
15:2 すると、パリサイ人、律法学者たちは、つぶやいてこう言った。「この人は、罪人たちを受け入れて、食事までいっしょにする。」
15:3 そこでイエスは、彼らにこのようなたとえ(単数形=一つのたとえ)を話された。
取税人、罪人たちがみな、イエスの話を聞こうとして近寄って来たその時、それを見ていたパリサイ人、律法学者たちがイエスに「この人は、罪人たちを受け入れて、食事までいっしょにする。」とつぶやいた。そうつぶやいたパリサイ人、律法学者たちに向かって、イエスは以下の3つのたとえ(羊のたとえ、銀貨のたとえ、息子のたとえ)を話されたのである。彼らはちょうどたとえの最後の部分に登場して父親を非難する兄息子のようである。彼らはイエスと共に喜べないでイエスを非難したのである。