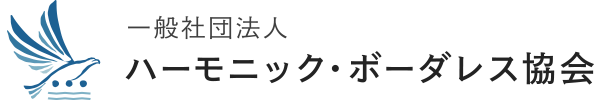特別記事2 失郷民
伽耶琴(民族の魂)
伽耶琴は大伽耶国の嘉賓(カシル)王が12の律呂を真似て十二弦琴を作り、これを干勒(ウロク)に作曲させてから、国情が逼迫すると、楽器を持って新羅に投降した。
6.25動乱(離散家族になってしまった)
国軍が咸鏡北道に駐留するとき国軍に志願入隊した北朝鮮の住民が多かった。これらは国軍が興南撤収することになり離散家族がなってしまった。写真は中共軍に対抗して国を守るために国軍3師団23連隊の指揮の下、軍事訓練を受けている咸鏡北道吉州出身の若者たちの姿である。
北朝鮮の捕虜からの失郷民
韓国には朝鮮戦争での北朝鮮の捕虜が16、7万人いた。捕虜の中には北朝鮮にいながら共産主義を嫌っていたが、強制的に徴兵された兵士も多かった。しかし、米軍は捕虜たち全部を、北朝鮮へ返せと命令していた。
だが、そのまま北朝鮮に強制的に返せば、北朝鮮で処刑される捕虜も多い。そのため当時、治安本部長だった文鳳済氏は李承晩大統領と相談し、捕虜たちの自由意志を尊重して北に帰りたいものは帰らせ、韓国にとどまりたいものはとどまれるように処置を下す決定をした。
これは米国側の意向を無視し、秘密裏に決めたものあり、南北が板門店で捕虜交換を行う前夜のことだった。
捕虜収容所の門を開けて、韓国にとどまりたい者たちは、闇夜に紛れて脱走させることにした。
これは、米軍には全く知らせず、当時の李承晩大統領が首をかけて決断した。
文鳳済氏は治安本部長として周到に準備し、実際の指揮をとった。
捕虜たちはその晩、囚人服を地面に埋め、支給した民間人の服を着て脱走、民間の家に隠れた。
最大の捕虜収容所だった巨済島からは約35,000人、あとでまた約20,000人を韓国内に逃がした。
中国人の捕虜約30,000人は自由意志で台湾に行った。その他インド、アルゼンチン、ブラジルなどに約1,000人が自由意志で行った。この数字は、文鳳済氏が挙げたものである。
「1953年6月18日、板門店での捕虜交換の前夜に決行しました。夜が明けてみると米軍はびっくりです。捕虜が大量に消えていたからです。もちろん北へ帰ることを希望したものは板門店で北朝鮮に帰し、韓国兵の捕虜と相互に交換しました。その数は約2万人でした」
捕虜を逃がしたことに対して最初、国内外から非難ごうごうだった。しかし、数日もすると賞賛の論調に変わり、「(捕虜交換を定めた)ジュネーブ協定の精神を見事に実行した」と、国際世論の支持を得るに至った。
解放された反共捕虜を見回している李承晩大統領
失郷民、それは働き続けること
失郷民たちは、素手で他郷(タヒャン)暮らし(サリ)(타향살이)で切り拓かなければならず、ひたすら働きつづけていた。生活基盤が何もないタヒャンサリで生き残る唯一の道は自ら金を持つことであり、そして子供達に高い教育を受けさせるこそ、彼らにタヒャンサリを生き抜く術を与えることになると認識していたからであった。金を持つことは、子供を教育し、身内のない他郷で病気や事故の場合の保証金となり、故郷へ戻る資金となるということで、タヒャンサリにおける命の網として考えられた。
そして、戦争への恐怖と不安は、避難民として南下を経験した失郷民の脳裏に焼き付いており、韓国に再び戦争が起きたことを想定し、金を蓄えておくことになる。戦争の終わっていない休戦状態であることを、彼らはタヒャンサリという高い代価を払って現実に体験しているからであった。戦争の恐怖と悲惨さを誰よりも実感している人々であったのである。
とりあえず食べていくこと、そして金を持つことに必死であった。そして、そのために、ひたすら働きつづけていた。これが失郷民ー世たちの姿である。タヒャンサリという厳しく険しい道程を、非常な覚悟で臨み、労働そのものを終わりなきものとして考え、消費に対する徹底した禁欲主義を貫くのであった。失業という言葉は、失郷民は似合わないものであった。とにかく仕事を見つけ出し、体を動かして金を稼ぐことが、タヒャンサリ一切の不安を取り除くことであると考えていたのである。
失郷民以外の韓国人には理解できないものがある。
失郷民の一世たちの考え方は、もはや命の綱としての価値をなくした金は社会に還元する。
社会に還元するという考え方には、失郷民以外の韓国人には理解できないものがあろう。伝統的価値観に基づく韓国社会では、血族間の絆を重視し、「男系血族」主義に基づく祭祀、戸主相続とともに財産も直系男子(主に長男)に承継することが当然のように考えられてきたからである。韓国戦争による、意図せざる核家族化とは言え、核家族化した失郷民の価値観は、韓国社会の伝統的家族制度の矛盾を切り崩す役割を果していると言える。
又、韓国の伝統社会は、日本統治・韓国戦争という近代以後韓国社会の歩みによって多く破壊されたが、そのような他者と戦争による破壊化過程は、戦後の権威主義的政治の長期化とも重なって、韓国人の価値観の歪みを生んだ。その歪みとは、労働は賎民がするものであり、「ヤンバン」(両班、朝鮮王朝時代の特権階級)は「働かずに優雅に暮らす」ことを理想、あるいは美学とする、ヤンバン思想の負の面だけを受け継いだ考え方が、かなり長い間、戦後韓国人の意識のなかを根強く占めていたことである。
「日本書紀」に貫かれている失郷民の悲痛(百済系)
百済州柔城 始降於唐 是時 国人相謂之曰「州柔降矣 事由奈何 百済之名 絶于今日 丘墓之所 豊能復往」 『日本書紀』天智三年九月条
百済の州柔城が落ちた。これをどうすればいいんだ。百済の名が今日で絶えたから、先祖の丘墓之所をどうして往復することができるだろうか?
祖国の山河(熊津)に置いて来た先祖の墓をこれからは往来できなくなったことを痛哭する断腸の悲哀であった。
一朝にして失郷の民となってしまったのだ。